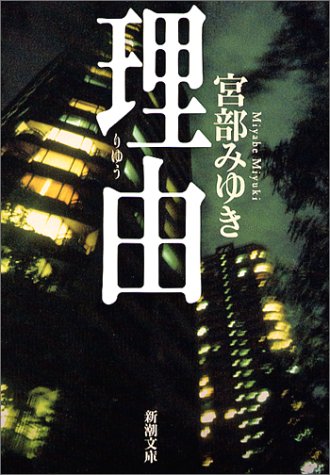東京都荒川区の超高層マンションの一室で起きた凄惨な殺人事件。
男女の死体と老婆の死体。そしてベランダから落下したと思われる若い男性の死体。
計4名の惨殺死体は、そのマンションの住人ではなかった・・・。
事件を中心に、膨大な数の関係者の証言をまとめた形で表現されるルポタージュの構成は、社会に潜む落とし穴を見事に浮かび上がらせる。
圧倒的な解像度で関係者間の関係性を活写する、極上のリアリティで綴られる大作。第120回直木三十五賞受賞作。
理由 (新潮文庫) | 宮部 みゆき |本 | 通販 | Amazonより引用:
事件はなぜ起こったか。殺されたのは「誰」で、いったい「誰」が殺人者であったのか――。東京荒川区の超高層マンションで凄惨な殺人事件が起きた。室内には中年男女と老女の惨殺体。そして、ベランダから転落した若い男。ところが、四人の死者は、そこに住んでいるはずの家族ではなかった……。ドキュメンタリー的手法で現代社会ならではの悲劇を浮き彫りにする、直木賞受賞作。
圧倒的解像度で描く「人間の営み」
磁石が砂鉄を集めるように、「事件」は多くの人びとを吸い寄せる。爆心地にいる被害者と加害者を除く、周囲の人びとすべてーーそれぞれの家族、友人知人、近隣の住人、学校や会社などの同僚、さらには目撃者、警察から聞き込みを受けた人びと、事件現場に出入りしていた集金人、新聞配達、出前持ち。数え上げれば、ひとつの事件にいかに大勢の人びとが関わっているか、今さらのように驚かされるほどだ。
この一文に象徴されるように、本作は膨大な数の「関係者」から、事件に関することや事件には直接関係ないことまで丁寧に聞き取っている。
そのひとつひとつの章がひとつの短編小説のように、詳細に、高解像度な筆致で描かれている。
それをさらにひとつにまとめたのが本作である、という体裁だ。
まずはその圧倒的な関係者の数に驚く。
ひとりひとりの描写が、実に細かく、まるで見てきたかのようなリアリティに満ちている。
このような、意図的に微に入り細に入った書き方をしているのは、それこそ「理由」がありそうだ。
舞台は1996年の夏に起こった事件を中心にしている。
1996年というと、バブルが弾けて、人々が熱狂から醒め、現実を見つつある、だがバブルの残り香がまだところどころに見られる、そんな時代だ。
まだバブルだった時期に計画され、建築された、ヴァンダール千住北ニューシティウエストタワーという、25階建ての高層タワーマンションを巡るこの事件の全容が解明されてから、ルポライターとおぼしき神視点の語り手によって綴られている。

おそらく、本作で著者が示したかったのは、「なぜ人は寄り添って生きていかなくてはならないのか」という問いなのではないだろうか。
バブルという酔狂な時代が終わってもなお、不動産に夢という甘いソースをたっぷりとかけて繰り広げられる人々の狂乱が続く。
そのなかで、上っ面だけで語られるニュースを賑わすだけのひとつの事件に、裏側にこびりつく真実を丹念にこれでもかと炙り出すことによって、人は好むと好まざるとに関わらず寄り合って生きていく生き物である、ということを静かに語っている。
ひとつの事件に紐付いた、ありとあらゆる関係者の、その背景にある生き様までを含めた物語を描くことで、多様な視点での「人間の営み」を描き出している。
人は人と関わり、偶然にしろ意図的にしろ、関わることで反応が生まれ、その反応に反応するかたちで新たな関係が生まれてくる。
そうした、現代社会にあってもなお、必要とされる人と人とのつながりや、気持ちの移りようを、うまく掬い上げられない社会構造を、諦観することなく描ききっているのだ。
バブルの時代も、バブル以降の時代も、そして現代も、一見して人々はつながりの希薄な、距離感のある生活をしている。
本作の時代との違いでいえば、スマートフォンの普及と、それに伴うSNSの浸透だろうか。
だが、SNSがもたらした、一見「繋がっている」感覚は、じつはとても希薄で緩やかなものだ。
気持ちの距離感は孤独感という形で、より広くなっているのかもしれない。
人と人との気持ちの距離感が開けば開くほど、誤解や勘違いや忖度や圧力や空気によって、さまざまなコミュニケーションロスが生じている。
そうしたロスがストレスという形で蓄積し、あるタイミングで爆発、大きな落とし穴が生まれてしまう。
その落とし穴に落ちてしまった者は、疑心暗鬼や憎しみにより、近くにいる人間を傷つけていく。
それが連鎖することで新たな犠牲者が、ひとりひとり、増えていくのだ。
「寄り添って生きて」いかないと、こうした「落とし穴」に陥ってしまうのだ。
ーーーネタバレ注意!ーーー


人は寄り添って生きていく社会的生物
ラストの章で、小糸孝弘がルポライター氏に語った最後の告白。
小糸孝弘はかつて自分の家だったウエストタワー2025号室に、砂川信夫たち疑似家族が「占有」していたころ、何度か間借りをさせてくれと申し出ている。
それは、自分の両親と暮らすよりも、おじさんおばさんたち(砂川たち)と暮らした方が楽だと思ったからだった。
そしてそれは八代祐司も同じだろう、と言う。
八代祐司も実の両親と暮らすよりも赤の他人である砂川たちと暮らした方が楽だと考えていたのだろうと。
もし、小糸孝弘自身が赤の他人と暮らしてきて成人したとき、邪魔になって砂川たちを殺してしまうのだろうか、と問うた。
この問いが示すのは、現代社会が抱える闇のひとつがここに確かにある、と著者が提示しているのではないだろうか。
明治から昭和の戦前あたりまで、大きな家族をひとつの生活単位とし、数世代が身を寄せ合って暮らしてきた時代から、戦後の高度経済成長を経て、だんだんと核家族化が進行した。
モノがあふれ、豊かになった(と錯覚した)現代人は、もっと豊かになりたいと考え、ますます密集した都市部へ集中する。
物理的な距離感はどんどん近くなるのに対して、心の距離感は逆にどんどんと遠くなっていった。
そうして、肉親であっても距離を詰められず、できるだけ触れ合わないような生活スタイルが浸透していく。
個人が個人として自立することとは別に、個人が孤立していく社会にあって、うまく距離感を保つには赤の他人と暮らした方がいいという価値観が広がっていくのだろう。
すると、どうだろう、まさにヴァンダール千住北で起こった一家4人惨殺事件が象徴するような、哀しい末路が再び起こらないとは限らない、と思わざるを得ないのだ。
そうした、現代の社会構造の歪さが、この事件で起こった背景にあるということだろう。
本作は、1996年9月2日から1997年9月20日まで「朝日新聞」夕刊に連載され、加筆されたのち、1998年5月15日に朝日新聞社から単行本が刊行された。
著者がその時代に見ていた「社会の落とし穴」は、その後埋まることはおろか、ますます広く大きくなっていると言える。
さらに2020年からのcovid-19によるコロナ禍により、人と人との距離感はますます、物理的にも広がっているのだ。
人の意思の力で、この「社会の落とし穴」を埋めることは、おそらく無理であろう。
解決には、社会制度やシステムをテクノロジーの力も使いつつ改善し、その後も価値観をアップデートし続けられるように、社会全体の問題として意識していくことくらいしか、思いつかない。
人は寄り添って生きていく社会的生物である。
そうしなければ「落とし穴」に落ちてしまうという「理由」があるからだ。