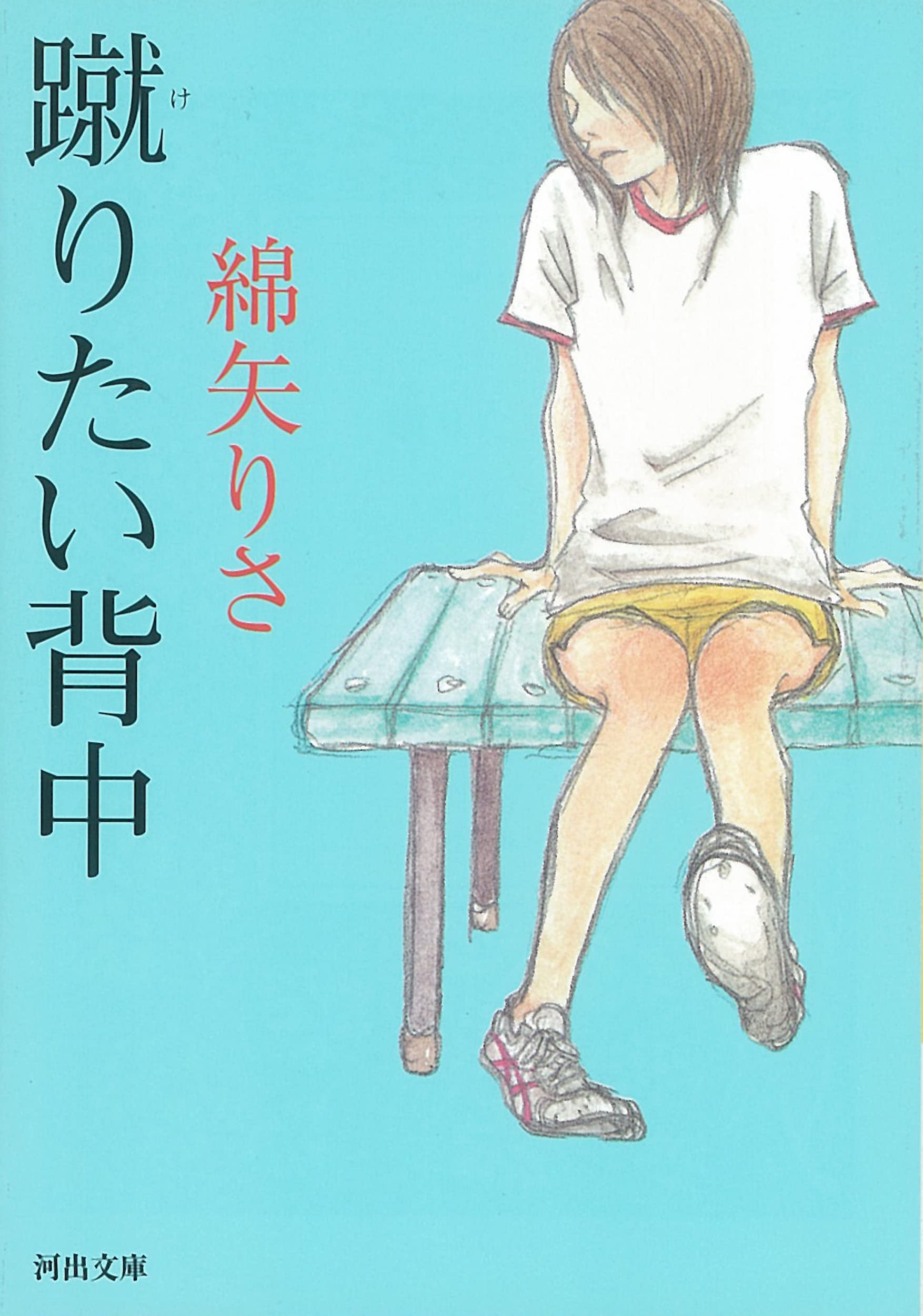2003年第130回芥川賞受賞作。
当時最年少での芥川賞受賞ということで話題になった。
「青春期特有の視野の狭さ」と「自分の立ち位置を確認したくて仕方がない心理」つまりアイデンティティへの渇望と模索を描いた「裏の」青春群像劇、として読んだ。
蹴りたい背中 (河出文庫) | 綿矢 りさ |本 | 通販 | Amazon
「青春期特有の視野の狭さ」というのは、読んで字のごとく青春の日々は何かにつけて盲目的であり、自覚はないが視野が狭く、小さな世界が世界の全てだと考えて行動してしまうことを指している。
生まれてから乳幼児期を経て、やがて思春期に差し掛かるころ、それまで身体の成長とともに精神的な成長も同時進行で進んできた「自分」の、身体と精神の成長スピードに差が生じてしまったことから、バランスを失ってしまう時期が誰にでも少しはあるだろう。
主人公・長谷川初美ことハツは、そうしたバランスを失ってしまっている時期に、運良くか運悪くか、同じクラスの「にな川」と出会う。
学校のクラスの、教室の中だけが世界の全てだと考えて授業の合間の10分間の休憩時間を退屈に過ごす毎日。
紙を細長くちぎって時間をやり過ごすくらいに、退屈な毎日を生きている。
クラスの中のどのグループにも属することなく、クラスの中の人間関係を観察し分析している。
そこには歴然とした「スクールカースト」が存在していた。
クラスの中は、見た目も華やかでコミュニケーション力が高く学校生活をエンジョイしている、今で言う「リア充層」と、見た目もコミュ力も高くなく、それを本人たちも自覚している「底辺層」とに大別される。
ハツはリア充層になれるはずもなく、かといって底辺層に属することも忌み嫌っていた。
そのせいでどのグループにも入れず、お昼ご飯もひとりで食べているような、みじめな(ハツ本人はそう考えていた)学校生活を送らなくてはならないという状況が描かれる。
一方のにな川は、授業中にも関わらず女性ファッション誌を眺める毎日。
大好きなファッションモデルの「オリチャン」にご執心だ。
ハツとは違って、にな川は周りから自分がどう見られているかは関心がない。
とにかく四六時中、オリチャンのことで頭がいっぱいなのだ。
「蹴りたい」とは? 「背中」とは?

タイトルの「蹴りたい」という部分は、ハツの心情であることは察しがつく。
何に対して「蹴りたい」とまで激しい感情表現になっているのだろうか。
一般的には、何かイライラしているとか、ストレスがかかっている状態を打破したいから「蹴りたい」という表現になると考えられる。
では、ハツは何に対していらついているのだろうか。
クラスのスクールカーストの中で、どのグループにも入れない自分に対して、と考えるのが自然な流れだろうか。
但し「背中」とは、おそらくハツ自身の背中ではなく、にな川の背中だろう。
にな川の背中を蹴りたいと思うハツの心情が、分かるとまでは私は言えない。
はっきり言ってしまえば、よく分からない。
だが、ハツがにな川に対して自分自身を見ていたとしたら、おそらく苛ついて蹴りたくなったのではないか、とは考えることができる。
ハツとにな川は大きな枠組みでは同類である。
クラスの中では底辺層にも入れない、はみ出し者同士だからだ。
だが、ハツははみ出し者のくせに周りから自分がどう見られているかを気にしており、気にしていながらそれを隠してまるで気にしていないように振る舞っている。
実に「拗らせている」という表現がぴったりくるのだ。
にな川は、自分がどう見られているかに関心がない。
頭の中は常に「オリチャン」だけである。
そして「オリチャンが大好きであらゆるグッズを集めているファンの鏡のような自分」がにな川のアイデンティティなのだ。
ーーーネタバレ注意!ーーー


そんなにな川の何がそんなに苛つくのか、ハツは「蹴りたい」だけでは収まらず、実際に背中に蹴りを入れる。
異常なほどのオリチャンファンであるにな川は、オリチャンの顔写真と首から下は別の女性タレントの水着写真とを切り抜いてテープで貼り合わせた(出来はお粗末な)「作品」を作ってしまうくらい、異常なのだ。
にな川のその異常性を目の当たりにしたとき、ハツは思うのだ。
”この、もの哀しく丸まった、無防備な背中を蹴りたい。痛がるにな川を見たい。いきなり咲いたまっさらな欲望は、閃光のようで、一瞬目が眩んだ。”
好きなものを愛し没頭すること自体は、誰にもあることで悪いことではないだろう。
だが、にな川の愛し方は、異常なほどの熱量であると同時に、ハツには「現実からの逃避」とも見えたのではないだろうか。
スクールカーストの底辺層にも入れないはみ出し者同士であるからこそ、その現実を直視できない自分(ハツ)の拗らせ方と、にな川のオリチャンへの執心は、形こそ違えど同じ種類だったのだろう。
青春ではあるが、表ではなく裏側を描いた群像劇
本作は決して明るい青春群像劇、ではなく、裏青春とでも言うべきか、屈折した拗らせた女子と現実逃避が過ぎる男子との裏のアオハルだ。
主人公はハツだが、同時ににな川の成長がほんの少し垣間見える群像劇とも読める。
それまでオリチャンを想い続け、常に女性誌を眺め、関連するグッズを買い集め、あらゆるインタビュー記事を読み込んできたにもかかわらず、実際に生のオリチャンを見たことはなかった。
それは「オリチャンファンである自分」がアイデンティティだったから、それでよかったのだろう。
だが、実際に生のオリチャンに会ったことがあるハツの存在が表れたことで、そのアイデンティティに葛藤が生まれる。
だからこそ初めてライブに行って生のオリチャンを見ようとしたのだろう。
そして初めてのライブ終わりの出待ちでオリチャンから一瞥もされず、同じファンとのトラブルまで起こしてしまったにな川は、オリチャンを遠い存在だったと感じてしまう。
普通に考えれば当たり前の光景なのだが、にな川にはそれがショッキングな出来事なのだ。
それだけ周りが見えていないということだ。

青春って、すごく密なので
2022年夏の甲子園大会の優勝校・仙台育英高校野球部監督は、優勝インタビューで「青春って、すごく密なので」との名言を残した。
「すごく密」であるはずの青春のまっただ中にいてもいいはずのにな川は、周りが全く見えておらず、また見ようともしていなかったからこそ、アオハルは訪れてこなかった。
唯一、オリチャンと会ったことがあるというハツが表れたことで、わずかな「密」が生まれた。
そのわずかな「密」が、わずかな青春の灯火のように揺らめいていた。
だが、それでも、まだ現実を見ようともしていないにな川の背中を、ハツはどうしても「蹴りたく」なったのだろう。
「まだ周りが見えてないのかよ」という気持ちと、「それでも周りを見ようとしないのかよ」という思いと、「いいかげんに自分がだめな奴だということを認めろよ」という心情の吐露がない交ぜになった「蹴り」を入れたのだろう。
そして同時に、にな川のまるまった背中にハツ自身の自分こそ最高にダサい奴であるという不甲斐なさや、何もしてあげられないのに自分を認めてもらいたい自己承認欲求の発露が、蹴りという形になって表出したのではないだろうか。
その表出の仕方も含めて、不器用で甘酸っぱい青春の味であろう。
もう私は、忘れてしまったが。