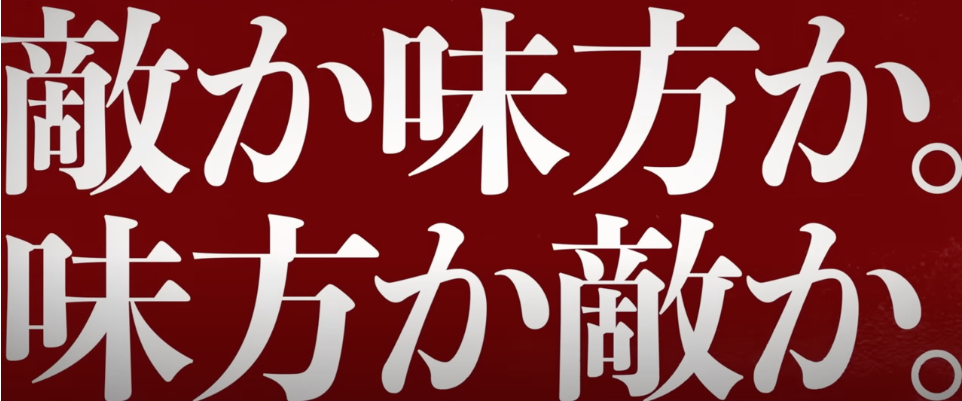NHKの大河ドラマを超えるスケール感、地上波の枠を超えた規模感、豪華キャスト、常識破りの放送時間延長放映、盛り上がる考察などなど、社会現象と言ってもいいくらいに話題となった。
他のテレビドラマのレビューは別記事に書いたが、『VIVANT』だけ保留としていたので、ここで記しておきたい。
・地上波の連続テレビドラマの強さ
・『日曜劇場』福澤克雄脚本ブランドと豪華キャストの強さ
・世界配信を意識した脚本とスケール感
この辺りはもうさまざまなメディアで語られているので、特筆して言うべきこともないだろう。
ノゴーン・ベキの贖罪

私が最も心揺さぶられたのは、役所広司演じる「ノゴーン・ベキ」の半生と散り際だ。
たたら製鉄の名家である乃木家に生まれたが、次男のため家を継ぐことはできなかった。
そのため東京大学へ進学後、警察官となり、公安外事課に配属されるまでになる。
バルカに潜入したのは1979年。
公安の任務ということは伏せた上で農業使節団として、現地での緑化事業に貢献。
砂漠の土地で作物がとれるまでに土壌を改良したことで「緑の魔術師(ノゴーン・ベキ)」と呼ばれるようになる。
1984年バルカ国内の内乱で命を落としたことになっているが、実際は救助を要請した公安に裏切られ、武装勢力に捕えられてしまう。
その時、妻は拷問で死に、息子である優介とは生き別れてしまう。
バトラカにより脱出できたものの、4年間優介を探し続けたが、日本人孤児は亡くなったと聞かされ、絶望する。
その頃、まだ乳児だったノコルと出会い、息子が割に育てることを決意する。
公安での知識を活かして、武器の扱いや狙撃を仲間に教え、武装勢力から守る用心棒を請け負い、孤児たちを助けていく。
「テント」を結成したノゴーン・ベキは、増え続ける孤児を救うため、孤児院を増やしていくが、より多くの資金を必要としたことで、テント自体の規模を拡大していった。
やがてバルカの地下深くに眠るフローライトの存在に気づき、土地を購入する資金を稼ぐため、国際的なテロ行為をも請け負うことになる。
フローライト事業を軌道に乗せることで、バルカ国内の経済も安定し、孤児も生まれなくなると考えたのだろうか。
これほどまでに壮大で、且つ大義に満ちた理念を胸に40年の月日を費やしてきた。
そして多くの孤児を助け、やがて孤児たちは大人になり、バルカという国を背負う人材になっていった。
だが、そこまでの壮大な半生、40年近くを費やしてきた時間と引き換えにしても、日本での「復讐」を諦めることはできなかった。
いや、この「復讐」の想いがあったからこそ続けて来れたのかもしれない。

最終話のラストで、ベキは妻の最後の言葉を持ち出し、望みを叶えようとする。
あとで優介がニコルに電話をしたことで判明したが、ベキやバトラカ、ピヨの銃に弾は込められていなかった。
本当は上原を殺すつもりはなく、脅すだけで十分だと考えていたのだろう。
それ以上に優介が追ってくることや自分を殺すことが任務であるからこそ、妻との間にできた実の息子である優介に最後に身を委ねたのではないだろうか。
それがベキの考える、罪を償う、という答えだったということか。
魅力的なキャラクターたちの「行動指針」
本作は放送開始前から事前情報を一切伏せられていた。
唯一ディザームービーだけが公開されていたが、内容の予想が全くできないものであった。
しかし、最終話まで観終わってから見返すと、すでに主要キャラクターの「行動指針」が示されていたことに気づく。
乃木憂助(堺雅人)は「信念」

優介は「美しき我が国を汚すものは何人たりとも許さない」と言い、国のために別班の任務に忠実に行動する。
最も優先されるべきは「愛国心」である。
テント内部へ潜入するためなら、別班のメンバーさえも騙し討ちするほどだ。
大義のため、任務のため、日本を守ることを優先するのだ。
野崎守(阿部寛)は「執念」

野崎も非常に優秀で、警察組織の中でもエリート集団である公安、その中でも外事課で活躍している。
日本とバルカ政府と世界各国とのせめぎ合いの渦中に入り込みながら、あくまでも「乃木優介を追う」という「執念」を見せる。
柚木薫(二階堂ふみ)は「愛」

薫さんは医療従事者として、バルカの地で多くの人に医療を施し、ジャミーンを助け、常に「愛」を与える存在として描かれていた。優介との束の間の幸せは、与えるばかりの彼女にとっても幸せな時間だったと思う。
黒須駿(松坂桃李)は「信頼」

黒須にとって乃木優介は別班メンバーの中でも特別な存在だったのだろう。
ベキからフローライト事業への手伝いを打診された後、優介とともに部屋に戻ったシーンでは、「俺にだけは…言ってほしかった」と優介に詰め寄っていた。それだけ特別に「信頼」していたのだろう。
ノゴーン・ベキ / 乃木卓(役所広司)は「正義」

ベキは決して「裏切り」を許さない。それは過去、公安に救助を要請し、ヘリがすぐそこにまで来ていたのに引き返されてしまった、公安の元上司に裏切られたからだ。
そして、内乱の後のバルカ国内の政情不安にも怒りを示す。
ワニズたちに説教していたのは、国としての「正義」は何たるかだった。
それぞれのキャラクターたちが何を欲し、何をしようとしているのかが、最低限わかりやすく示されていた。
このおかげで、テレビドラマとしての(分かりやすさの)及第点を担保しつつ、「敵か味方か。味方か敵か。」のコピー通り、敵味方が目まぐるしく入れ替わっても、視聴者を置いていかない作りになっていた。

テレビドラマを「プロダクトアウト」で魅せた
マーケティング用語で「マーケットイン」と「プロダクトアウト」という言葉がある。
マーケットインとは、顧客ニーズを起点に製品やサービスを開発すること。
対するプロダクトアウトは、自社の技術や方針など優先して製品を開発することをいう。
これまでの民放テレビ局が制作するテレビドラマは、連続ドラマであれ、単発ドラマであれ、いずれもマーケットインの思考で作られていたように思う。
明確に証拠があるとか、現場にいたわけでもないので、単なる感想でしかないと言われれば、まさにその通りである。
だが、テレビから目を離してもストーリーについていけるように、できるだけ登場人物にセリフで説明させるなどが行きすぎているように感じるのは確かだ。
また、明るいキャラクターはいつも明るくてよく喋り、力自慢のキャラクターは大抵いつもあまり頭が良くなかったり、ステレオタイプなキャラクターがほとんどだし、キャラクター自体に深みがないことがほとんどだ。
現実世界では明るい人でも落ち込むことがあるし、スポーツができて頭がいい人などたくさんいる。
ドラマはフィクションなので現実世界と同じでなくても良いのだが、分かりやすさを求めるあまり、リアルっぽさがなくなってしまい、それが作品全体の魅力を引き出せなくなっているのではないだろうか。
『VIVANT』は、これは断言しても良いと思うが、プロダクトアウトの思考で作られている。
ヒントはその放映時間にある。
通常の連続テレビドラマは、放送枠が56分程度で、CMを除くとドラマ本編は45分程度だろうか。
大体1クール3ヶ月の間で10話分を放映するのがスタンダードだろう。
たまに、力を入れている作品では初回だけ15分拡大スペシャルと銘打って放映することがあるが、概ね毎週同じ時間枠で組まれている。
だが『VIVANT』は最初から放映時間がバラバラだったのである。
| ・第1話 | 21時 – 22時48分の54分拡大放送 |
|---|---|
| ・第2話 | 21時 – 22時19分の25分拡大放送 |
| ・第3話 | 21時 – 22時9分の15分拡大放送 |
| ・第5話 | 21時 – 22時9分の15分拡大放送 |
| ・第9話 | 21時30分 – 22時49分の25分拡大放送 |
| ・最終話 | 21時 – 22時19分の25分拡大放送 |
これがプロダクトアウトの発想である。
つまりどういうことかというと、通常のドラマは時間枠ありきでドラマの内容を編集し、時間枠内に収めて放映する。
これはマーケットインの考え方であると先に述べた。
市場(視聴者)の向けて、こうして時間枠を綺麗に割り振っていた方が、見やすいだろう、という発想である。
プロダクトアウトの考え方では、ストーリーとしてキリがいいところで区切る、という作り方をする。
そのほうが面白くて、視聴者に楽しんでもらえるのであれば、既存の時間枠も無視して、作品の都合で放映時間を決めていく。
これがプロダクトアウトの発想である。
これには、製作陣からの絶対的な自信が伺える。
この作品は面白い、視聴者も楽しんで見てくれるに違いない、絶対にヒットさせるのだ、という矜持のようなものを感じる。
民放テレビ(特に地上波)は、広告収入によるビジネスモデルなので、マーケットインと言いながら実際はスポンサーを向いて作られている。
スポンサーに広告料を出してもらうためには、システマチックに時間を概ね均等に割った上で売っていく方が楽なのだ。
だが、現在それではもはや通用しない時代になってきているように思う。
Netflixやfulu、Disney Plus、U-NEXTなどのサブスク配信サービスが台頭してきている。
ひと昔前から比べても益々目の肥えた視聴者に振り向いてもらうためには、内容の濃い、手間暇かけたコンテンツを作っていかなければならないのだ。
視聴者の大半はこれまで見たこともないような驚きのある物語を求めている。
マーケットイン発想では視聴者の想像の範囲内のものしか作れない。
時間枠ありきで編集されたドラマと、ストーリーが面白いことを最優先したドラマでは、どちらが支持されるかは明らかだろう。
テレビドラマの歴史的転換点となる作品『VIVANT』

これまでのテレビドラマの常識を悉くアップデートしてしまった作品であったことは間違い無いだろう。
これから10年20年経ったとき、あの『VIVANT』以前と『VIVANT』以後に分けられる、と言われる時がくるのだろう。
今後のテレビドラマのビジネスモデルすら変えてしまうかもしれない作品だ。
だからこそ、(きっとあるであろう)続編を待ちたいと思う。