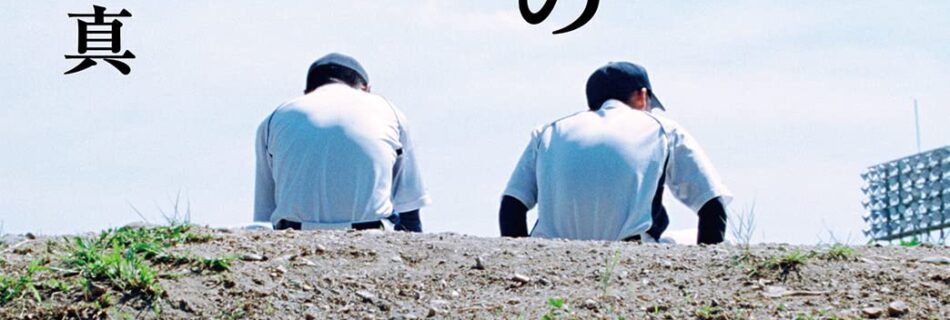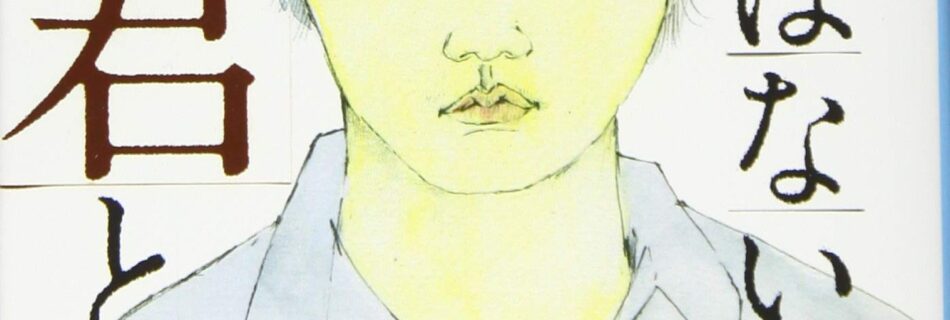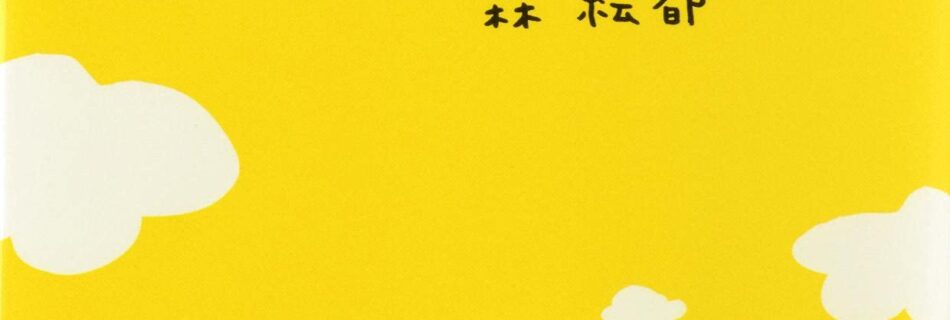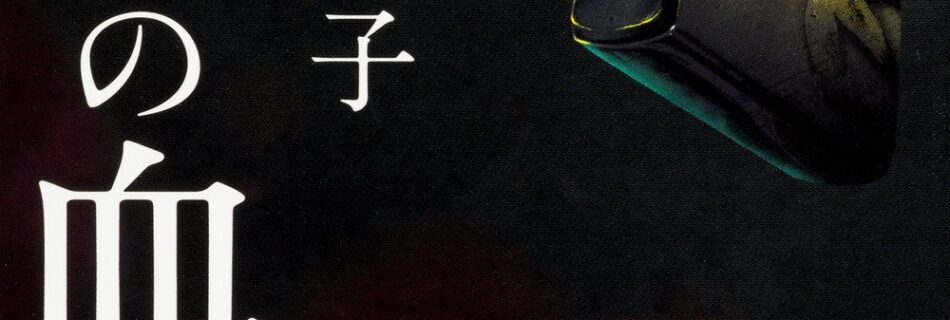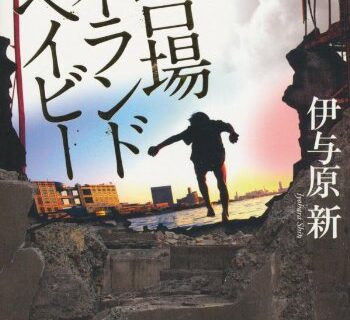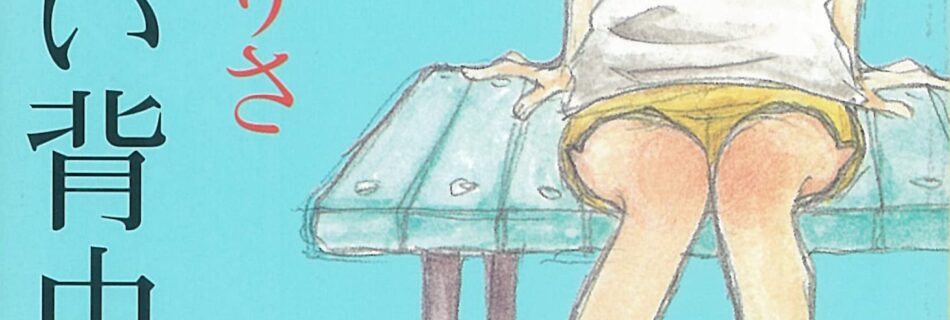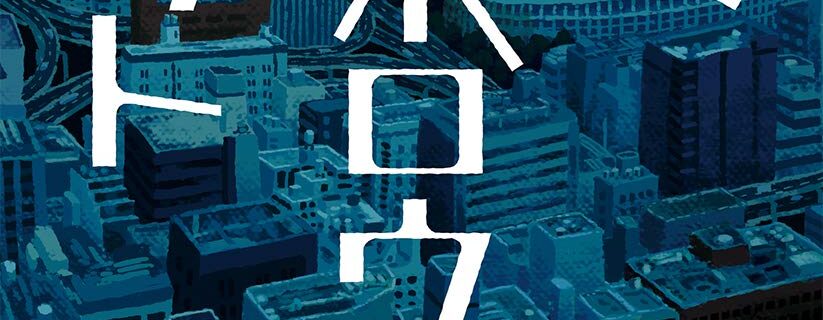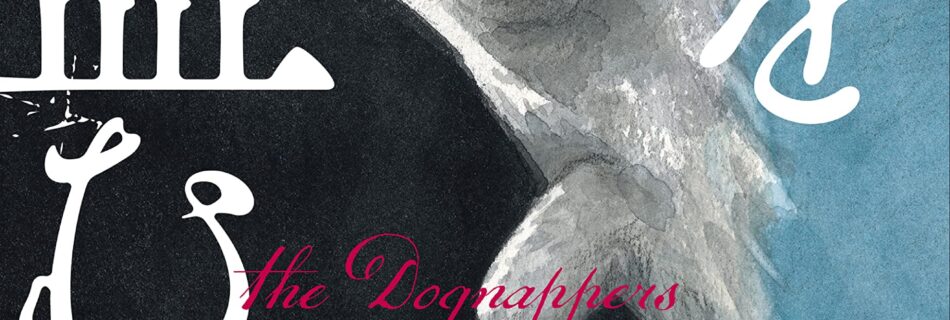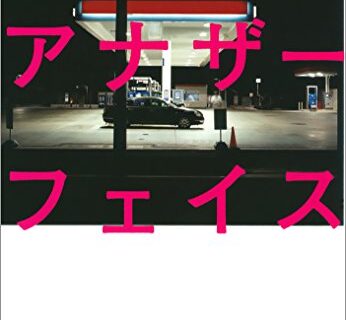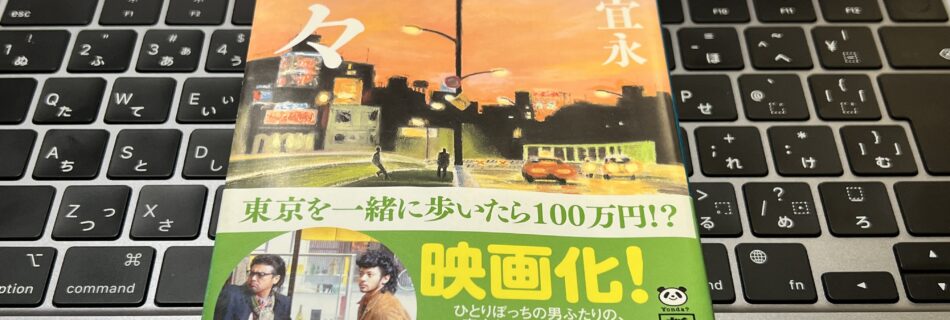【BOOK】『あしたの君へ』柚月裕子:著 心の内側に寄り添う仕事
「家庭裁判所調査官」と聞いて、どんな仕事なのかを説明できる人は、そう多くないだろう。
それだけ普段の生活には馴染みがない職業である。
本書はその家庭裁判所調査官になる、前段階の「調査官補」が主人公の連作短編集。
家庭裁判所調査官に採用されたばかりの新人・望月大地は2年間の養成過程研修で九州・福森家裁に配属される。
新人ではあるが実際の少年事件を担当するなかで、表面には見えてこない心の内側に、その人にしかわからない真実があることに気づく。
それは必ずしも良いことだけとは限らない。
相談者と彼らを取り巻く家族との抗いがたい葛藤と苦悩を共に考え、向き合うことで、望月大地自身もまた成長していく物語。